【PR】本ページはアフィリエイト広告による収益を得ています。
幾田りらの新曲「Voyage(ヴォヤージュ)」は日本テレビ『DayDay.』で 3年連続で開催の高校ダンス動画コンテスト【LOVEダン2026】の課題曲となっています。
この記事では「幾田りら」の「Voyage(ヴォヤージュ)」の歌詞の意味についての考察と歌詞に含まれるワードについての豆知識を書いています!
気軽に楽しみながら豆知識を増やしていきましょう〜!
幾田りら Voyage(ヴォヤージュ) 歌詞
まだ半端な夢に帆を張って 荒波へと繰り出す
どれほどの痛みが押し寄せても 受ける覚悟はある
無謀だって無様だって 無駄があったっていい
不安だって不満だって 全部抱えてこう
※歌詞は現時点で判明している部分を耳コピしたものになります。
幾田りら Voyage(ヴォヤージュ) 歌詞考察と豆知識
それでは歌詞考察と豆知識を合わせて書いていきます!
“Voyage”が示す人生の航海のはじまり
「まだ半端な夢に帆を張って 荒波へと繰り出す」という一節は、夢が未完成のままでも行動を起こす勇気を象徴しています。
ここで注目したいのが、曲タイトルにもなっている“Voyage”という言葉です。
“Voyage”はフランス語の「voyage(旅行)」に由来し、さらに語源をたどるとラテン語の「viaticum(旅支度、旅のための糧)」にたどり着きます。
つまり“Voyage”とは単なる「航海」ではなく、「旅立ちの準備と覚悟」を内包する言葉なのです。
この語源を踏まえると、「半端な夢に帆を張る」というフレーズは、未熟な状態でも“完璧な準備を待たずに出航する”という強い意思を感じさせます。
人生はいつだって「準備万端」ではなく、荒波の中でこそ自分の夢が育っていくというメッセージが込められているようです。

“Voyage”の語源「viaticum」は、古代ローマでは旅に出る際に神官から授けられる「旅の祝福」や「携行食」を意味していました。
これは後にキリスト教の聖体拝領の意味も持つようになり、人生を“神聖な旅”と捉える思想にもつながります。
“荒波”に隠された日本文化の象徴
このフレーズでは、痛みや困難を「押し寄せる波」にたとえていますが、日本文化において“波”は特別な象徴を持ちます。
特に浮世絵の名作《神奈川沖浪裏》(葛飾北斎)にも見られるように、大波は自然の圧倒的な力、すなわち「人間の意志では抗えない運命」や「試練」を象徴してきました。
この曲でも「荒波」は単なる障害ではなく、夢を現実に変えるために越えなければならない“人生の大きな力”として描かれています。
「痛みが押し寄せる」という表現は、波の連続性=試練が一度では終わらないことも示唆しています。

日本の古語では、「波風を立てる」は単にトラブルを意味するだけでなく、「人間関係や社会に波乱を起こす」という意味でも使われていました。
歌詞の“荒波”は、個人的な苦難だけでなく、社会的な逆風や人間関係の揺らぎまでも含んでいる可能性があります。
“否定語”の反復が示す強靭な心
このフレーズは、否定的な言葉を並べながらも、それらを丸ごと受け入れる姿勢が印象的です。
「無謀」「無様」「無駄」と、すべて“無”で始まる言葉を連続させることで、ネガティブな感情を一気に引き受ける決意が感じられます。
ここで興味深いのが、“無”という漢字の語源です。“無”はもともと古代文字では「踊る人」を描いた象形文字でした。
後に“何もない”という意味に転じましたが、元来は「動き、舞う」という意味があったのです。
つまり「無」を連ねるこのフレーズは、もともと“静止ではなく、動き”を孕んだ文字でもあるわけです。

“無”の甲骨文字は、人が両腕を広げて踊る姿を描いており、「霊的な舞い」「神秘的な力」を意味していました。
つまり、「無謀・無様・無駄」という否定語の中には、本来“止まらずに動き続ける力”が潜んでいるという、逆説的な深みがあるのです。
幾田りら Voyage(ヴォヤージュ) 歌詞考察と豆知識 まとめ
『Voyage』は、未完成な夢を胸に、それでも出航する人生の姿を描いた楽曲です。
語源や文化的背景を踏まえると、この曲は単なる「旅立ちソング」ではなく、“準備が整わなくても、波にのまれながら進む覚悟”を称える歌だとわかります。
曲タイトルの“Voyage”が持つ「旅の糧・神聖な旅」という意味と、歌詞全体に流れる「不完全なまま進む強さ」が見事に重なり合い、聴く人それぞれの“人生の航路”に寄り添う作品となっています。
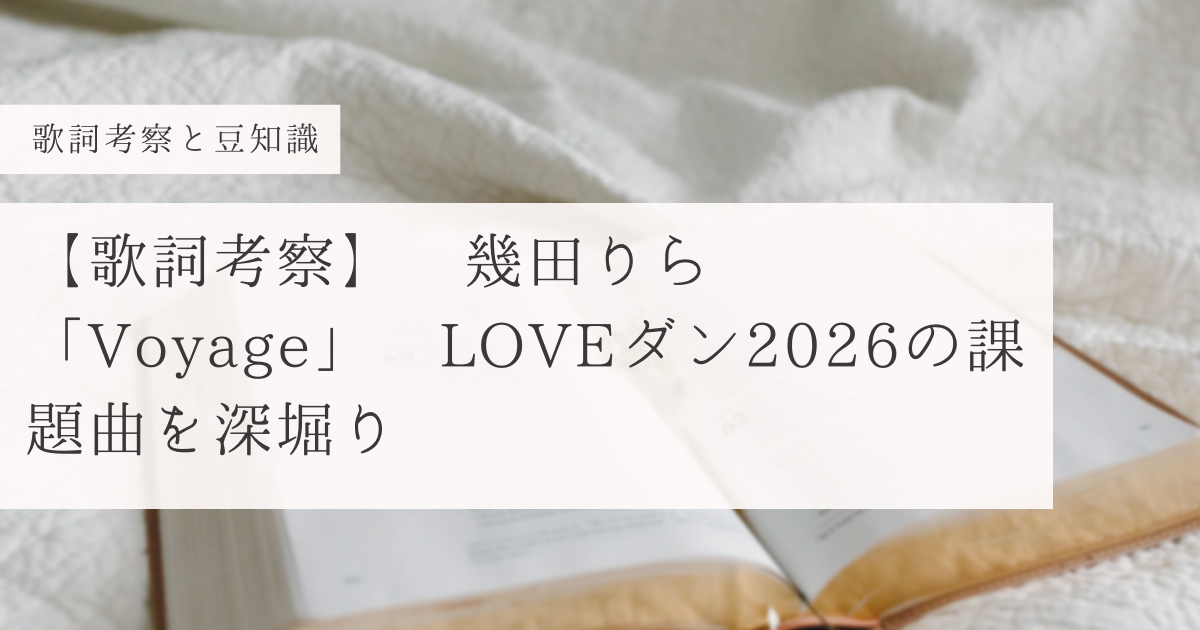
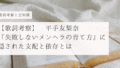
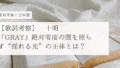
コメント