【PR】本ページはアフィリエイト広告による収益を得ています。
tuki.(ツキ)の新曲「人生讃歌」は10月24日(金)公開の映画『愚か者の身分』の主題歌となっています。
この記事では「tuki.(ツキ)」の「人生讃歌」の歌詞の意味についての考察と歌詞に含まれるワードについての豆知識を書いています!
気軽に楽しみながら豆知識を増やしていきましょう〜!
tuki.(ツキ) 人生讃歌 『愚か者の身分』主題歌 歌詞
正しさはひとつじゃないのに
答えもひとつじゃないのに
押し付けないでよ 君の価値観
正解を求めるのは
答案用紙だけでいい
日々忙しいから忘れるが
行きつく場所は同じ
皆美しい 皆美しい
生きたいように生きたくて
人生美しい 人生美しい
そう思えればいいのに
画面の中の誰某に
石を投げる人もきっと
笑ってなんかない そう信じたい
正解が解らないから
寝つきが悪くなるの
追い詰められるほど頑張るのは
ほんとは誰のため
皆美しい 皆美しい
生きたいように生きたくて
人生は苦しい 人生は苦しい
そんな風に思わなくていい
「愛されたい」の気持ちのために
誰かを傷つけたりしないように
明日は今日より素敵になるように
君がほんの少し笑えるように
変われますように
涙や痛みはもういいでしょう
ここまで頑張って来たんでしょう
もう報われてもいい頃でしょう
私は私らしくでいいでしょう
皆美しい 皆美しい
生きたいように生きたくて
人生美しい 人生美しい
そう思えればいいのに
「愛されたい」の気持ちのために
誰かを傷つけたりしないように
明日は今日より素敵になるように
君が苦しまなくていいように
願い叶いますように
tuki.(ツキ) 人生讃歌 歌詞考察と豆知識
それでは歌詞考察と豆知識を合わせて書いていきます!
道徳と罪のあいだで揺れる“愚か者”たち
映画『愚か者の身分』において、主人公たちは犯罪という「間違い」を犯しながらも、どこかに“善”を求めようとしています。
歌詞の冒頭で語られる「正しさはひとつじゃないのに」という一節は、まさにその葛藤の核心です。
彼らは社会の“正義”から外れた存在でありながら、心のどこかで「自分なりの正しさ」を信じている。
この歌詞は、そんな彼らの“救われたい魂”を代弁しているのです。

「正しさ」という言葉の語源は、古語の「正し(ただし)」で、「真っ直ぐ」「ゆがみのない」という意味を持ちます。
しかし日本語の「正しさ」は、道徳的・宗教的な「善悪」とは異なり、“社会の中で整合していること”を指します。
つまり「正しさ」は絶対ではなく、時代や立場で変化するもの。
『人生讃歌』は、そうした「変わりゆく正しさ」を背景に、“愚か者”の生き方にも美しさを見出そうとしているのです。
“人生讃歌”というタイトルに込められた仏教的まなざし
この曲のサビに繰り返される「皆美しい」「人生美しい」という言葉。
それはまるで、地獄のような世界に身を置く登場人物たちへの“供養の言葉”のように響きます。
闇に生きる彼らを単なる犯罪者として断罪するのではなく、「それでも美しい」と歌い上げるこの構成は、どこか“仏教的”です。

“讃歌(さんか)”という言葉は、仏教用語の「讃歎(さんたん)」に由来します。
これは、如来や菩薩の徳を褒め称えることを意味します。
つまり『人生讃歌』とは、「人生」という名の苦しみの連続を、それでも尊いものとして讃えるという意味を持つのです。
苦しみも悲しみも、“人として生きた証”として称える視点こそ、この歌の根底にある“慈悲”の心です。
『愚か者の身分』においても、タクヤたちは決して救われるわけではありません。
それでも、この曲は彼らの存在そのものを否定せず、「皆、美しい」と赦している。
その姿勢が、“讃歌”という言葉の最も深い意味に重なります。
人が罪を犯す根源的な理由
歌詞の後半に登場する「『愛されたい』の気持ちのために 誰かを傷つけたりしないように」という一節。
この言葉は、タクヤやマモルたちの心の叫びと完全に一致しています。
彼らは本来、誰かに認められ、愛されたかっただけ。
しかしその願いが満たされぬまま、歪んだ形で“生きる手段”を選んでしまったのです。

心理学者アブラハム・マズローは、人間の欲求を「生理的欲求」から「自己実現欲求」までの5段階に分けました。
その中で「愛と所属の欲求」は、生きる上で欠かせない中核に位置しています。
人は“愛されたい”と願う生き物であり、それが満たされないと、犯罪・依存・虚栄などの「代替的行為」に走る傾向があります。
『人生讃歌』は、そうした人間の本能的な弱さを否定せず、「それでも願い続けていい」とそっと肯定しているのです。
この歌のラストで繰り返される「君が苦しまなくていいように 願い叶いますように」というフレーズは、まるで“自分を許せない者”が、他者への祈りによって救われようとする儀式のようです。
愛を知らずに育った者が、最後にたどり着いたのは“他者への祈り”。
その構図こそ、『愚か者の身分』という物語の救いそのものです。
tuki.(ツキ) 人生讃歌 歌詞考察と豆知識 まとめ
『人生讃歌』は、闇に生きる若者たちの罪や苦しみを糾弾する歌ではありません。
むしろ、彼らがどんなに不器用であっても、「生きたい」と願ったこと自体を讃える歌です。
タイトルの「讃歌」は、“正しい者”への賛美ではなく、“愚かでも愛を求めた者たち”への鎮魂歌なのです。
人生は、美しい。
それは“綺麗だから”ではなく、“苦しみながらも誰かを想うことができるから”。
この歌が教えてくれるのは、そんな人間の尊さなのです。
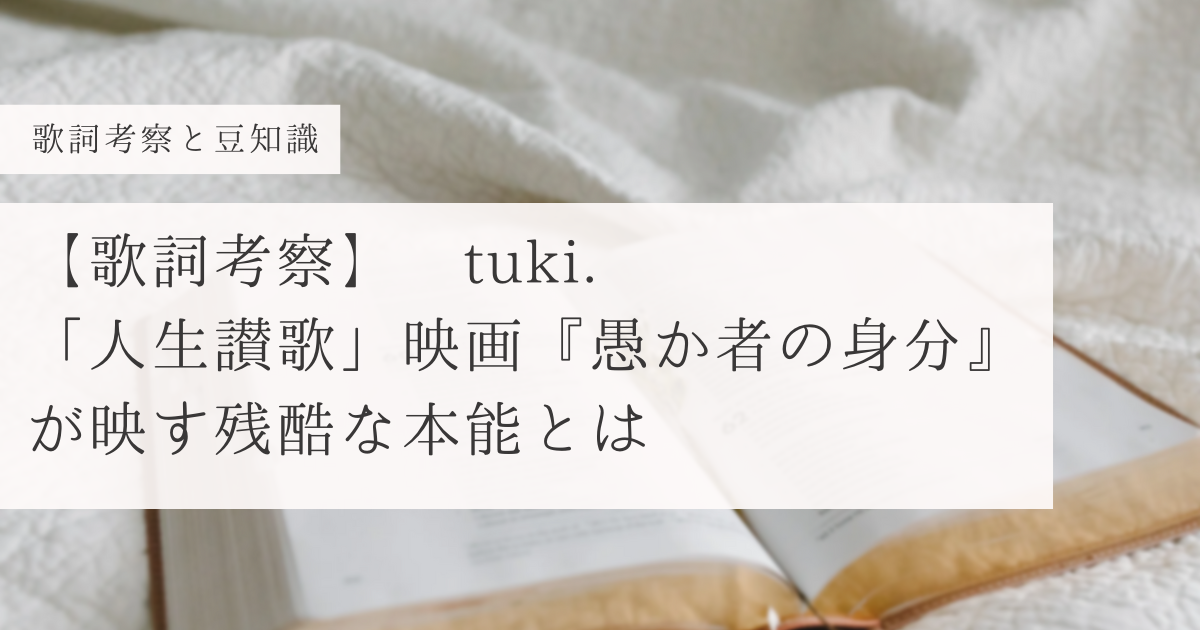
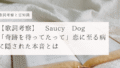
コメント