【PR】本ページはアフィリエイト広告による収益を得ています。
この曲は8月8日公開の映画「近畿地方のある場所について」の主題歌となっています。
この記事では「椎名林檎」の「白日のもと」の歌詞の意味についての考察と歌詞に含まれるワードについての豆知識を書いています!
気軽に楽しみながら豆知識を増やしていきましょう〜!
椎名林檎 白日のもと 歌詞
ただ歩いている案山子(かかし)。北東へ向かって二駅三駅と。
何一つ欠いていない。急にふとそう思えて、東京を踏み締めている。
染井吉野の木立。中央線沿いに根差し開(はだ)かる。ほら、目を瞑っても、
射し込んで滲(し)みて来る嫩葉(どんよう)。青々と酸っぱい太陽。
いまという未来。
私がイメージしたことあったっけ。いいえ、まだ新緑の眩しささえ、
愛せずにいる。
土曜の正午過ぎ。神保町と後楽園は弾(はじ)き合う。上下六車線の大通り、
暗黙の国境をなぞっている。ねえ、どうしたいの。過去に帰りたい。
かつては全知全能だったっけ。いいえ、いまも。私の胸に唯一の愛、
姿だけ変える。最初は深海。やがて夜空を経て洞窟まで。転身の度、
肥大する存在。砕けそうだ。あなたはもういないと、この身を抉って
丸めたとして。
体自体が記憶を遺すデバイス。投げ捨てたいのを堪えて生き存えている。
この世の果てに一人のあなたを宿したまま覚えたままでいたい。
静かなる攻防。
椎名林檎 白日のもと 歌詞考察と豆知識
それでは歌詞考察と豆知識を合わせて書いていきます!
案山子が歩く?「ただ歩いている案山子」に見る東京という記憶の風景
歌い出しの「ただ歩いている案山子」。
この比喩的な存在にまず驚かされます。
案山子(かかし)といえば、畑に立っている不動の存在。
ところが歌詞では「歩いている」。
これはつまり、心だけが歩いている抜け殻のような状態を示しているのではないでしょうか。
舞台は東京。
北東へ向かって、二駅三駅と移動する中で「何一つ欠いていない」と感じる描写からは、都会の喧騒の中に漂う“満たされた虚無”のようなものが漂います。
〈豆知識:案山子の語源に隠された意味〉

「ねえ、“案山子”って、どうして“かかし”って読むか知ってる?」

「え、あれってそのまま音読みじゃないの?」

「実は“嗅がし”が語源なんだよ。
昔は獣よけに臭いものをぶら下げてたから、“嗅がす=かがす”が変化して“かかし”になったんだって。」

「怖っ…見た目じゃなくて匂いだったんだ。じゃあ“案山子が歩く”って、存在してるだけで記憶を刺激するような、残り香みたいな感じかもね。」
案山子とは、人の形をしていながら人ではない存在。
その案山子が歩くことで、心だけが記憶の地図をたどっているようにも感じられます。東京という「記憶の舞台」を歩くことで、過去に埋もれた感情がふと呼び起こされる。
歌詞の“踏み締めている”という言葉にも、その記憶の再確認のようなニュアンスがこめられているのかもしれません。
「染井吉野」と「嫩葉」が語る、まだ愛せない“いまという未来”
「染井吉野の木立。中央線沿いに根差し開かる」という描写は、春の情景を感じさせますが、同時に“いま”が受け止めきれない主人公の葛藤も読み取れます。
特に注目すべきは「嫩葉(どんよう)」。
この言葉は、若葉よりもさらに柔らかく、まだ赤みを帯びた葉を指します。
「青々と酸っぱい太陽」という表現と組み合わさることで、まだ眩しさを受け止めきれない未成熟な心が浮かび上がります。
〈豆知識:嫩葉(どんよう)は“青葉”ではない〉

「“どんよう”って読むの、難しいね。どんな意味か知ってる?」

「え、若葉ってことじゃないの?」

「若葉よりもさらに新しくて、まだ完全に緑じゃない、赤ちゃんの葉っぱのことなんだって。」

「えー!じゃあ“愛せずにいる”のは、成熟した今じゃなくて、生まれたての“未来”そのものなんだ…」
「いまという未来」という矛盾するような表現にも、今この瞬間に生きているはずなのに、まだそれが「未来」としての形を持てていない、そんな宙吊りの感情がにじみ出ています。
嫩葉とは、希望でありながらもまだ愛せない不確かな何か。
その“酸っぱさ”を感じることで、私たちも自分の「未成熟な今」と向き合うことになるのです。
「体自体が記憶を遺すデバイス」──変容し続ける愛と、“静かなる攻防”
後半に登場する印象的なフレーズが「体自体が記憶を遺すデバイス」。
これは、愛する人の不在と向き合いながらも、忘れずに“生き延びる”覚悟を示す一文です。
その直前には、「あなたはもういない」と嘆きつつも、「最初は深海、やがて夜空を経て洞窟まで」と愛が変容し続ける描写が続きます。
深海、夜空、洞窟と暗く広がる空間をめぐるようにして、その“存在”は変質していくのです。
〈豆知識:デバイスという言葉の進化〉

「“デバイス”って今はスマホとか思い浮かぶけど、もともとの意味って知ってる?」

「うーん、機械とか道具のこと?」

「実は“思案”とか“策略”って意味もあったんだ。ラテン語の“divisus”(分ける)に由来するんだよ。」

「ってことは“記憶を遺すデバイス”って、体が単なる容器じゃなくて、記憶を“分け持ってる”ってこと?」

「そう。“一人で背負い込む”んじゃなくて、体と一緒に共存している記憶のことなんだと思うよ。」
最後の「静かなる攻防」という言葉もまた印象的です。
これは、忘れてしまいたいという衝動と、それでも記憶していたいという願いの綱引き。
表面的には穏やかに見える日常の中で、心の中では激しい戦いが続いているのです。
椎名林檎 白日のもと 歌詞考察と豆知識 まとめ
タイトルの「白日のもと」とは、本来は隠されたことが明るみに出るという意味で使われます。
歌詞全体を通して見ると、この「白日」とは、自分の中に秘めていた記憶や感情が否応なしに明るみに出てしまう瞬間を指しているように思えます。
案山子のように無自覚に歩き、嫩葉のように未熟な“いま”に戸惑いながらも、記憶を刻み続ける身体。そのすべてが「白日のもと」にさらされ、静かに、しかし確かに“いまを生きる覚悟”へとつながっていくのです。
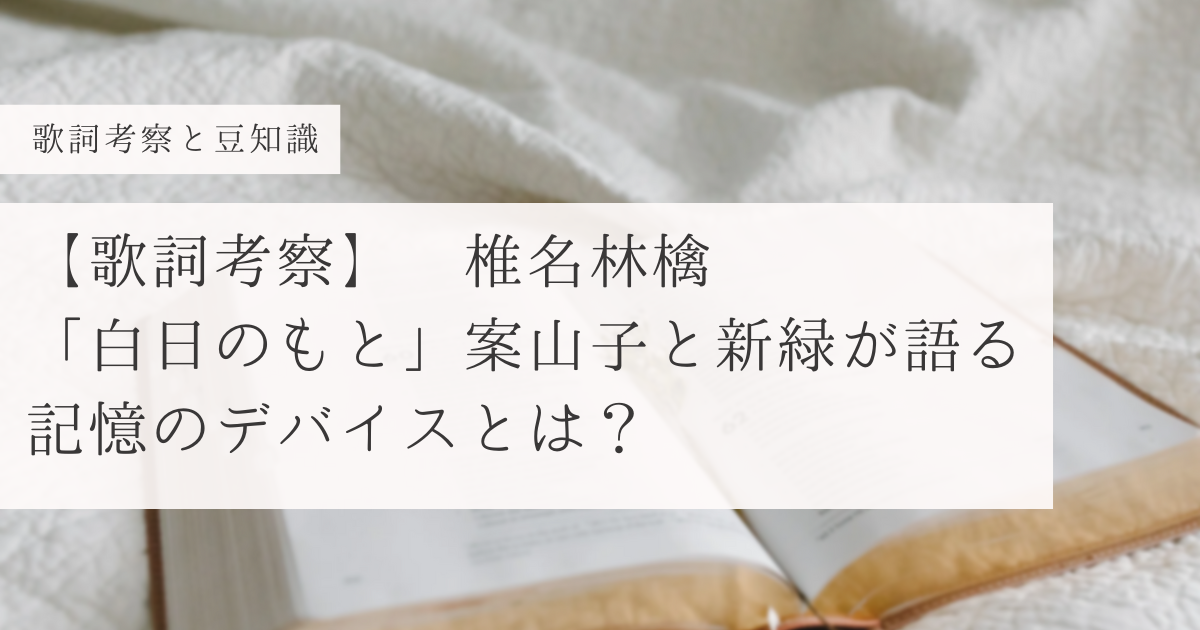
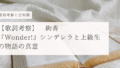
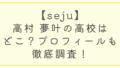
コメント