【PR】本ページはアフィリエイト広告による収益を得ています。
INIの新曲「君がいたから」は10月31日公開の映画「INI THE MOVIE『I Need I』」主題歌となっています。
この記事では「INI」の「君がいたから」の歌詞の意味についての考察と歌詞に含まれるワードについての豆知識を書いています!
気軽に楽しみながら豆知識を増やしていきましょう〜!
INI 君がいたから 歌詞
いつか 選んだ道は
間違いなんかじゃないと
言えるから。
この旅路は
始まったばかりさ
折れそうな日も そばには
頼れる仲間がいつも
忘れない 重ねた日々を
今も胸の奥で 静かに光る
進む先に 何があろうとも
居場所はあの日から
ここだと決まったから
駆け抜けてきた道も 立ち止まる日も
Thinking back, 君の声がして
何者でも無かった僕を
照らしてくれたのも君で
何度目かな ぶつかっては また抱き合って
ただ分かる そんな日々が宝物で eh
僕ら抱いた 夢に
変わらない 想い掴んで
曇りのない 晴れの日も
雨の夜も
進む先に 何があろうとも
背中の翼で
何度も羽ばたける
いつだって 君の笑顔みると
この道以外考えられないって
深い闇だって 君と漂えば
僕たちのdrama 彩るOSTになるさ
感じてきたこと
歩んできた時
違うけど
手を取り合って
What I need is you
繋がる
どんなに遠くても 道に迷っても
振り返れば すぐそこに
君がいたから
この声が 響き渡る空
あの日交わした 約束と
見てきた 景色すべて
夢の続きを ともに
INI 君がいたから 歌詞考察と豆知識
それでは歌詞考察と豆知識を合わせて書いていきます!
「いつか選んだ道は間違いじゃない」―道という言葉が持つ日本的ニュアンス
歌詞の冒頭で「いつか選んだ道は間違いなんかじゃない」と歌われます。
ここで注目したいのは「道」という言葉。
単に進む方向を示すだけではなく、日本文化では「道(どう/みち)」は生き方そのものを表す言葉として用いられてきました。
剣道・茶道・華道といった「〇〇道」にも見られるように、道とは一生をかけて歩む精神的な軌跡を意味します。
つまり、この歌詞の「道」は「人生」や「志」を含んだもの。だからこそ「間違いじゃない」と言い切れる強さが響くのです。

「道」という漢字は、首(人の頭部を意味する象形)と「しんにょう(道を表す偏)」からできています。
つまり「道」はもともと「人が通る道筋」と「進む方向を示す頭(首)」を合わせた文字。ここから「人の進むべき方向=人生のあり方」という意味が派生しました。
「背中の翼」―翼はなぜ「希望」の象徴になるのか
中盤に出てくるフレーズ「背中の翼で 何度も羽ばたける」。
翼は自由や希望の象徴として多くの歌で使われますが、そのルーツは神話にあります。
ギリシャ神話のイカロスは翼を得て空へ舞い上がり、キリスト教文化でも天使の翼は神と人間を繋ぐ媒介でした。
翼は「人を超える力」「限界を越える可能性」を象徴してきたのです。
この歌詞では「背中の翼」は自分の努力だけでなく、仲間や「君」の存在によって与えられた力を示していると考えられます。

日本語の「翼(つばさ)」の語源は「つば(端)」に「さ(接尾辞)」がついたもの。
つまり「つばさ」は「物の端っこ」から派生した言葉で、鳥の羽の外側=飛翔を支える部分を指したのが始まりです。
翼という言葉そのものに「外へ広がる」「未来へ広がる」というニュアンスが含まれているのです。
「君がいたから」―居場所を決める存在の力
サビに繰り返されるタイトルのフレーズ「君がいたから」。
この一言は、ただの恋愛表現ではなく「存在が自分の居場所を決めてくれる」という強い意味を持ちます。
日本文化には「居場所」を大切にする価値観があります。
江戸時代の儒学者・貝原益軒は『養生訓』の中で「人は己の居る所を得て安んず」と記しました。
つまり、人は正しい居場所を得てこそ心が安定するという考え方です。
この歌詞の「居場所はあの日から ここだと決まった」という表現は、まさに人生の軸を与えてくれた「君」への感謝の宣言だといえます。

「居場所」という言葉は比較的新しい日本語で、江戸時代後期から一般に使われるようになりました。
それ以前は「居所(いどころ)」や「在処(ありか)」が用いられていました。
「居場所」という響きには、物理的な場所だけでなく「心が落ち着く場所」というニュアンスが含まれているのです。
INI 君がいたから 歌詞考察と豆知識 まとめ
『君がいたから』というタイトルは、単なる愛の歌にとどまりません。
「道」は人生の選択を肯定し、「翼」は仲間や君に支えられて得た希望を象徴し、「居場所」は人の存在が与える心の拠り所を意味しています。
つまりこの歌は「誰かの存在が、自分の人生を意味あるものに変える」という普遍的なメッセージを届けているのです。
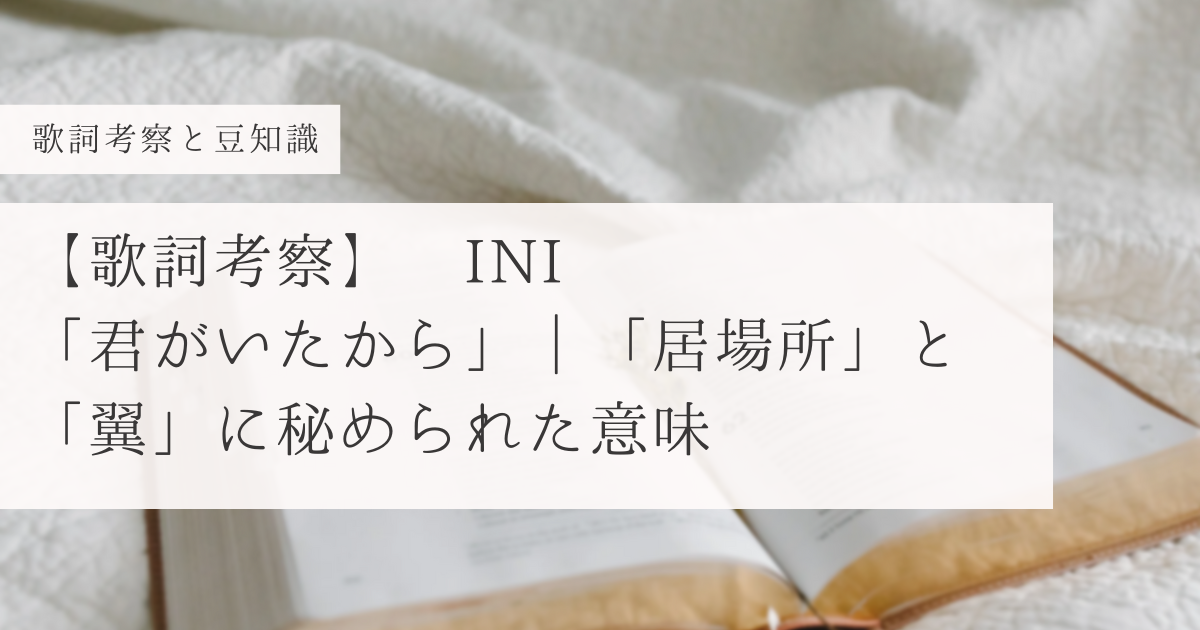
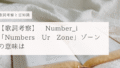
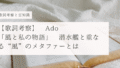
コメント