【PR】本ページはアフィリエイト広告による収益を得ています。
こっちのけんとの新曲「ごくろうさん」は8月31日より配信開始されました。
なぜ音楽を続けるのか、何を歌うべきなのかという根源的な問いに立ち返った作品となっています!
この記事では「こっちのけんと」の「ごくろうさん」の歌詞の意味についての考察と歌詞に含まれるワードについての豆知識を書いています!
気軽に楽しみながら豆知識を増やしていきましょう〜!
こっちのけんと ごくろうさん 歌詞
LaLaLa
なんのうたに⼼を打たれ
⽣きてきたのか覚えているか
僕らのうたにそれらはあるか
⾒失うほど熱くなるもの
LaLaLa
無いはずさ
かけ離れた僕ら
きっとそれが⾃分らしさ
無いはずさ
まだ明るい明⽇
きっとこれが⾃分なんだ
負けてもいいから僕ら
痛みはするがくじけるもんか
強がって何度も⽣きてくれよ
悔しさが怒り出したか?
誰かのために疲れるもんさ
ごくろうさんで⽣きてくれよ
LaLaLa
誰のことを愛し続けて
⽣きてゆくのか覚えているか
僕らの未来置いてあるのは
息を呑むほど
幸せなこと
だからいいのさ今は
⼒の限り⼒を抜いて
転がって何度も逃げてくれよ
負けてもいいから僕ら
誰かのために⽣きてるもんさ
ひとりぽっちで死んでいくなよ
明⽇がこわくなったら
僕らが磨いたまんまるな声を
欲しがって何度も⽣きてくれよ
LaLaLa
こっちのけんと ごくろうさん 歌詞考察と豆知識
それでは歌詞考察と豆知識を合わせて書いていきます!
「なんのうたに心を打たれ」―歌が人生を形づくる記憶
冒頭のフレーズ「なんのうたに心を打たれ 生きてきたのか覚えているか」は、音楽が人生に深く結びついていることを問いかけています。
私たちはふとした瞬間に、特定の歌が人生の記憶や感情を鮮やかに蘇らせることを経験します。
ここで注目したいのは「うた」という言葉の古い用法。
万葉集では「歌(うた)」は単なるメロディではなく、人の魂や祈りを託す「言霊」として扱われてきました。
この歌詞でも「うた」は記憶や生き方の根源にある存在として描かれており、日本文化の歌に対する独特の捉え方が反映されています。

「歌(うた)」の語源は「うち吐(は)く」=心の中を吐き出す、という説があります。
つまり「うた」とは感情や魂を吐露する行為そのものであり、古代から歌は人生を語る手段でした。
「ごくろうさんで生きてくれよ」―労いの言葉が持つ二面性
サビで繰り返される「ごくろうさん」という言葉は、一見すると軽い労いのフレーズに聞こえます。
しかしこの表現には、日本語特有のニュアンスが隠れています。
「ごくろうさん」は本来、目上から目下にかける言葉で、「ありがとう」とは微妙に異なる立場性を含みます。
つまり単なる感謝ではなく、「大変だったな、その努力を認めるよ」というニュアンスを持つのです。
この歌詞では、その労いの言葉を仲間や大切な人に対して投げかけることで、社会的なヒエラルキーを超えた優しさへと変換しています。

江戸時代には武士が家臣に対して「ご苦労であった」と声をかけるのが礼儀でした。そのため現代でも「ご苦労さま」は目上から目下に使う言葉とされます。
一方、「お疲れさま」は上下を問わない表現。
この微妙な違いを知っていると、日常会話でも意外に役立ちます。
「ひとりぽっちで死んでいくなよ」―共同体の声が宿る歌
終盤に出てくる「ひとりぽっちで死んでいくなよ」という強い言葉は、孤独を突き破ろうとする切実な呼びかけです。
ここでは、個人の生を超えた「声の共同体」が浮かび上がります。
「僕らが磨いたまんまるな声」という表現が象徴的です。
「まんまる」は日本文化において「円満」「完全」「和」を意味する形容。
つまりこの歌詞は、個人の声ではなく、仲間や社会と響きあう「円(まどか)な声」によって未来を生き抜くことを提示しています。

「まんまる」という言葉は古語の「円(まどか)」に由来し、「欠けることなく調和している状態」を指します。
日本の家紋や茶碗の形にも「円」が多いのは、円形が「和」を象徴するからなのです。
こっちのけんと ごくろうさん 歌詞考察と豆知識 まとめ
『ごくろうさん』というタイトルは、一見すると軽やかな労いの言葉ですが、実は「他者を認め合いながら共に生きる」という深いメッセージを持っています。
歌詞全体を通して伝えられるのは、「ひとりで抱え込まずに、仲間の声を頼りに生き抜け」という励まし。
「ごくろうさん」という表現が持つ歴史的背景やニュアンスを知ると、この曲が単なる応援歌ではなく、日本文化の根底にある“和の精神”を体現した歌であることに気づかされます。
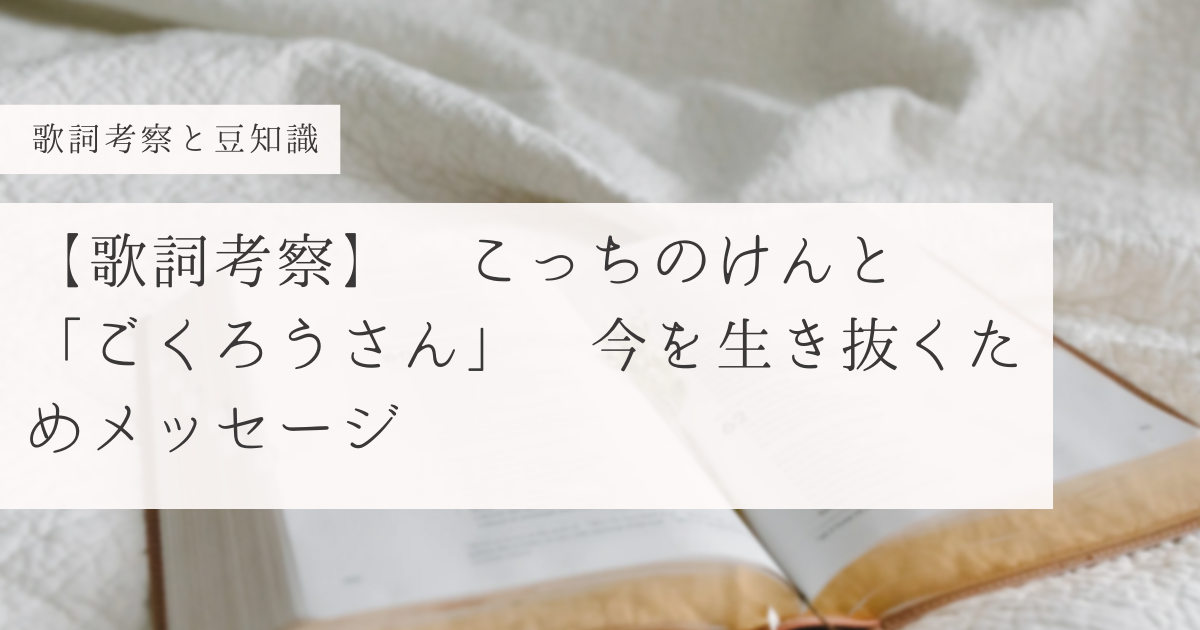
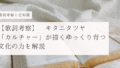
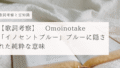
コメント