【PR】本ページはアフィリエイト広告による収益を得ています。
RADWIMPS(ラッドウィンプス)の新曲「筆舌(ひつぜつ)」は10月8日にリリースされたニュー・アルバム『あにゅー』に収録されている楽曲となっています。
この記事では「RADWIMPS(ラッドウィンプス)」の「筆舌(ひつぜつ)」の歌詞の意味についての考察と歌詞に含まれるワードについての豆知識を書いています!
気軽に楽しみながら豆知識を増やしていきましょう〜!
RADWIMPS(ラッドウィンプス) 筆舌(ひつぜつ) 歌詞
電話帳の中の人が少しずつ死んでいったり
唯一行きつけの居酒屋は潰れ変な店に変わったり
あんなに好きだった人が結婚して子供も産まれたり
その後シングルマザーになり久しぶりに連絡がきたり
ATMまで行って金貸した脚本家の彼は今や売れっ子だけど
あの時のなけなしの5000円はまだ返ってきてなかったり
生きてりゃ 色々あるよな
生きてりゃ 色々あるよなぁ そりゃそうだよなぁ
そりゃそういうもんだな
ダチの腹に癌が見つかりなんかヤケに食らったり
いつ死んでもいいとか言ってた俺も検査に行ってみたり
小3だったあの生意気な親友の子供は今じゃ
高校にあがり親の金くすねコンドーム買っていたり
このペースで時が過ぎるなら一人ぼっちで死ぬ可能性が現実味を帯びて
人知れずぽつんと死ぬなら夏場は嫌だななんて思ったり
生きてりゃ 色々あるよな
生きてりゃ 色々あるよなぁ
きっとこれからだって想像をゆうに超えてこいや
「ずっと」とか「絶対」とか「一生」とかないのはもうわかったから
せめてもう少しだけこのままで ねぇこのままでいさせて
失ってからしか気づけないような出来損ないとわかってるんだ
それなら俺は 俺をあと何回無くせば気づけるんだろう
君はいないのに 全然いなくなんないのは ねぇなんでなんだろう
あの頃バンドを始めた仲間はほぼ辞めていたり
今の流行は歌って踊ったりヒップホップが占めていたり
「ただいま」も「おかえり」もない日々が人生の半分以上を占め
「それと引き換えに手にした喜びがあるじゃねぇかよ」なんて言い聞かしたり
「かつて音楽は人間の手によって作られた時代があったんだよ」なんてさ
そんな時代を前にまだ見ぬとんでもねぇ音楽を作りてぇなんざほざいたり
生きてるって そういうもんだろ
生きてるって そういうもんだろ
きっとこれからだって そうありたいと思っちまうのさ
「ずっと」とか「絶対」とか「一生」とかないのはもうわかったから
せめてもう少しだけこのままで ねぇこのままでいさせて
例え「さよなら」が来るとしても 出逢えた喜びでおかしくなんだ
俺は俺をあと何回だって 何回だって繋ぎ止めるよ
君はいないのに ずっとずっとここにいるのはねぇなんでなんだよ
あの行きつけの店の店長は自殺だったこと
死ぬ3日前連絡があったけど 出られなかったこと
生きてりゃ色々あるよな
生きてりゃ 色々あるよな
生きてりゃ色々あるよな
生きてりゃ 色々あるよな
RADWIMPS(ラッドウィンプス) 筆舌(ひつぜつ) 歌詞考察と豆知識
それでは歌詞考察と豆知識を合わせて書いていきます!
“筆舌”が意味する「言葉の限界」
「電話帳の中の人が少しずつ死んでいったり」
というフレーズは、まるで何気ない独り言のようでありながら、時間の残酷さと「言葉にならない感情」の端緒です。
ここで曲のタイトル「筆舌」が意味を持ち始めます。
「筆舌に尽くしがたい」という表現がありますよね。
これは「筆(書くこと)」と「舌(話すこと)」、つまり文字と音声という二つの表現手段をもってしても伝えきれないほどの、深い思いや衝撃を示す慣用句です。
「筆舌」はその一節を切り取った言葉。タイトルそのものが、この歌詞全体を貫く“表現しきれない人生の痛み”を象徴しています。
さらに、電話帳というアイテムにも時代背景があります。
スマホが普及する以前、人々のつながりは「電話帳」に記録され、死や引っ越しによってそこから名前が少しずつ消えていくというのは、かつての世代特有の感覚です。
デジタル時代の「ブロック」や「アカウント削除」とは異なり、「死」によって消えていく“連絡先”の静けさが、この歌の導入に重みを与えています。

「筆舌に尽くしがたい」は平安時代から使われた表現で、『大鏡』や『源氏物語』にも類似の言い回しが見られます。
もともと「尽くす」は「限界まで表す」という意味。つまり、「筆舌」は“人間の表現力の限界”を一言で示す象徴的な語なのです。
“死”の季節感と日本人の感性
「夏場は嫌だななんて思ったり」という一節は、一見軽い口調ながら、日本人の「死と季節」に対する感性がにじみ出ています。
実は、日本の文化では「夏の死」は忌避される傾向があります。
理由の一つは「遺体の腐敗」が早い季節であること。
江戸時代の文献や俳諧にも「夏の死」はしばしば哀れや不憫として詠まれており、たとえば与謝蕪村の句にも「夏の死」に対する季節的な湿度と感情が込められています。
また仏教的にも、盂蘭盆(お盆)の季節と重なり、“死者が帰る季節”という感覚があるため、生者の死が重なることを嫌う風習もあります。

「夏場の死を嫌う」という感覚は俳句の季語にも表れていて、「夏の死」は直接の季語にはなりませんが、「夏安居(げあんご)」や「盆」のように死者との境界が薄れる時期として古来から意識されていました。
つまり「夏場は嫌だな」という軽い一言には、深い文化的背景が潜んでいるのです。
永遠という幻想と日本語の“言霊”
歌詞の後半で繰り返されるこのフレーズは、曲全体のクライマックスです。
若い頃に信じていた「永遠」や「絶対」は、現実の人生のなかで静かに崩れていく。
しかしそれを“冷めた皮肉”ではなく、“受け入れと祈り”として歌っている点に、この曲の深みがあります。
ここで注目したいのが「ずっと」「絶対」「一生」といった言葉そのものです。
これらは日本語特有の「時間の永続」を曖昧に包み込む言葉であり、西洋の「forever」や「eternity」とは微妙にニュアンスが異なります。
日本語には古来、「言霊(ことだま)」という考え方があり、言葉には霊的な力が宿ると信じられてきました。
「ずっと」や「一生」といった語が持つ“甘い永遠の幻想”は、まさにこの言霊信仰の延長線上にあると言えるでしょう。

言霊思想は『万葉集』の時代から見られ、日本は「言霊の幸(さき)わふ国」とも呼ばれます。
これは、発した言葉が現実を形作ると信じられていたためです。
つまり「ずっと」「絶対」という語を口にすること自体が“永遠を信じようとする祈り”の行為でもあるのです。
RADWIMPS(ラッドウィンプス) 筆舌(ひつぜつ) 歌詞考察と豆知識 まとめ
「筆舌」というタイトルが示す通り、この歌は「言葉では表しきれない」人生の喪失と時間の重みを描いています。
電話帳の変化、友の病、季節と死、そして永遠という幻想。
そのすべては私たちの人生にも静かに流れています。
だからこそ、歌詞の淡々とした描写が、かえって胸に突き刺さるのです。
生きてりゃ色々ある。
それを言葉にできないからこそ、音楽がある。
この曲はまさに「筆舌に尽くしがたい」人生の一瞬を刻みつけています。

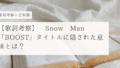
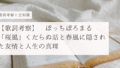
コメント