【PR】本ページはアフィリエイト広告による収益を得ています。
このDigital Single「未確認領域」は8月11日(月)先行配信リリース となっています。
この記事では「Number_i(ナンバーアイ)」の「未確認領域」の歌詞の意味についての考察と歌詞に含まれるワードについての豆知識を書いています!
気軽に楽しみながら豆知識を増やしていきましょう〜!
Number_i(ナンバーアイ) 未確認領域 歌詞
So like a 事後のベッドメイキングみたいにぶっ壊して
Break it
ブッ飛ぶ 上空と
離れた手をずっと追うよ
壊そう go sign
未確認領域
未確認領域
未確認領域
未確認領域
未確認領域
未確認領域
未 ay ay ay ay
I see the light
※歌詞は現時点で判明している部分を耳コピしたものになります。
Number_i(ナンバーアイ) 未確認領域 歌詞考察と豆知識
それでは歌詞考察と豆知識を合わせて書いていきます!
So like a 事後のベッドメイキングみたいにぶっ壊して —— 破壊から始まる再構築
このフレーズは、整えることを放棄した後の「ぶっ壊し」。
まるで失敗した関係や、やり直しの効かない過去を整えることに意味はないと断じて、次に進む覚悟のようなものを感じさせます。
「事後のベッドメイキング」は、終わったことを取り繕うむなしさの象徴とも取れます。
会話形式の豆知識:語源「メイキング(making)」と破壊の対義

ねえ、「ベッドメイキング」って普通は整える行為でしょ?でもこれ、実は中世英語の「maken(作る)」が語源なんだ。

へえ!じゃあ「make」って、元々「形を与える」とか「整える」って意味だったの?

その通り。だから「メイキング」は「作り直す」「形にする」ってニュアンスを含むんだけど、「事後の」ってつけられてるから、もう終わったあとに形にするむなしさが強調されてる。

なるほど、それで「ぶっ壊して」になるんだ。「整える」=「無駄」っていう価値観の転倒だね。

まさに。破壊の中にこそ本当の再生があるっていう、パンク的な思想かも。
離れた手をずっと追うよ —— 「空」に浮かぶ手と失われたつながり
「ブッ飛ぶ 上空」と「離れた手」という描写は、現実感のない切なさを感じさせます。
手を取り合う=つながりや理解の象徴とすれば、それが「離れて」しまったことで、追いかけるのは幻想に近いものになっています。
会話形式の豆知識:宗教美術に見る“空を漂う手”の象徴

この「離れた手」ってさ、西洋の宗教画にも出てくるんだよ。たとえば神の手が雲間から伸びてくるやつ。

あ、あれってアダムに手を差し伸べる神の絵だよね?

そうそう、ミケランジェロの『アダムの創造』。あれって、人間が神性とつながる象徴でもある。

ってことは、この曲の「離れた手」も、つながるはずだった理想との断絶を示してるかも?

まさに。しかも「上空」とセットにしてるから、手の届かない理想や記憶をずっと追い続けてる感があるんだよね。

届かないと分かってても、追わずにはいられない…それが切なさの正体かも。
未確認領域 × I see the light —— カオスの中で光を見出す
そしてこのフレーズ「未確認領域」の反復が印象的です。
繰り返すことで、恐れや不安よりも、その“未知”に向かう姿勢が際立っています。
最後に「I see the light」とあることで、この領域の中に“光”を見出していることが分かります。
会話形式の豆知識:未確認領域=“リム”(liminal space)という概念

「未確認領域」って、心理学や文化人類学では“リム”って概念に近いんだよ。

「リム」って何?聞いたことないかも。

liminal space=境界領域。通過儀礼の途中の、どっちにも属してない状態を指すんだ。

つまり、子どもでも大人でもない…“変わり目”ってこと?

そうそう。だから「未確認領域」って、実は“変わる途中の自分”を描いてるのかもしれない。

なるほど…最後の「I see the light」は、その混沌を抜けた先の自分の姿かもね。
Number_i(ナンバーアイ) 未確認領域 歌詞考察と豆知識 まとめ
「未確認領域」というタイトルは、未知の場所というよりも、未知の自分自身や、壊れた関係の先にある新しい在り方を示しているのかもしれません。
“事後のベッドメイキング”では、「壊れた過去を整えること」に意味がないと気づき、その先にある「混沌とした未確認の領域」に向かって歩き出す物語です。
繰り返される「未確認領域」のリフレインと、最後の「I see the light」は、迷いと希望の狭間で光を見つけた瞬間の詩的な描写なのです。
破壊から始まる再生、そして“未確認”こそが希望に変わるというメッセージ。まさに今の時代を生きる私たちのテーマそのものです。
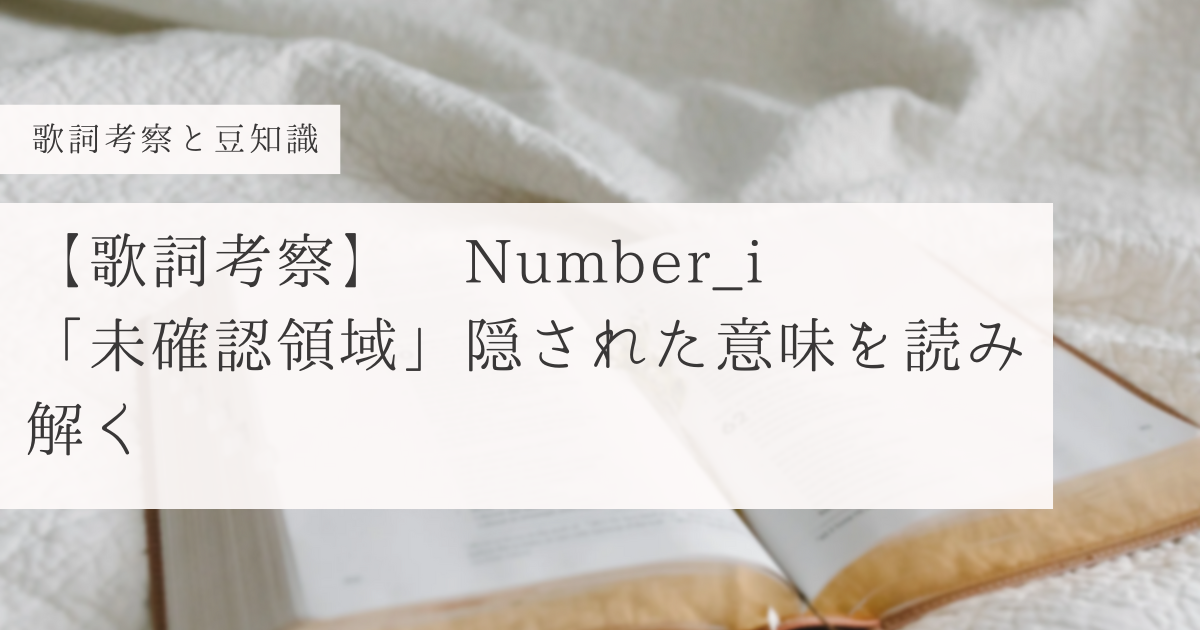
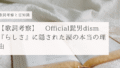
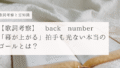
コメント